三浦綾子(みうらあやこ)の人生と文学が語る信仰①
愛の証しの文学、すべては「道ありき」から始まる
森下 辰衛(もりした・たつえ)
三浦綾子読書会講師
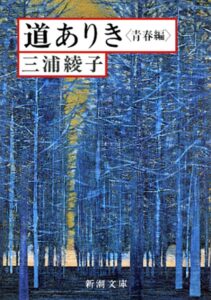 三浦文学は作家自身が人生で出会った真実に裏打ちされた文学である。そしてその中は、『道ありき』に書かれた絶望から光へと導かれた経験である。敗戦後の絶望と罪責感、死の病との闘いのなかで、キリスト者前川正(まえかわ・ただし)に愛されてキリストと出会い、彼の死後現れた三浦光世(みつよ)に励まされて癒され、結婚するに至った物語である。
三浦文学は作家自身が人生で出会った真実に裏打ちされた文学である。そしてその中は、『道ありき』に書かれた絶望から光へと導かれた経験である。敗戦後の絶望と罪責感、死の病との闘いのなかで、キリスト者前川正(まえかわ・ただし)に愛されてキリストと出会い、彼の死後現れた三浦光世(みつよ)に励まされて癒され、結婚するに至った物語である。
その核心は、彼女自身が語るように「私を変えた愛」だった。苦しみの道の途中で出会った男たちの愛とその背後にあった神の愛、それが彼女をどう変えたかという証しなのだ。
三浦綾子(旧姓・堀田)は1922年に北海道旭川市で生まれ、両親と十人兄弟の大家族の中で育ち、1939年、17歳で小学校の教師になる。大戦へと傾斜する時代、彼女は「あなたたちはお国のために命をお捧げするのですよ」と教えた。それは命がけの愛のはずだった。しかし、日本が敗け命じられた教科書の墨塗りは、彼女自身の人生に墨を塗ることに他ならなかった。時代が変われば全否定されるようなことを信じて、そのために死になさいと教えた自分。子どもたちの前に顔を上げられない、愛していたがゆえの痛み。もう生きていけないほどの挫折、絶望、罪責感はまさに彼女の命を凍えさせる<氷点(ひょうてん)>だった。教師を辞めた彼女は二重婚約をするが、結納の日に倒れ、当時は死の病だった肺結核の宣告を受ける。しかし彼女は「ザマアミロ」と呟(つぶや)くのだった。『道ありき』巻頭には「われは道なり、真理なり、命なり」という聖句が書かれている。しかし彼女には道がなく、信じられる真理もなく、心と体の命も失いかけていた。けれど彼女がこんなどん底から歩み始めたことは幸いだった。なぜなら三浦綾子はこの壮絶な物語に「道ありき」と名づけて、それでも神は道を備えてくださるという真理を希望として語る者になったからだ。彼女が陥(おちい)った闇が濃ければ濃いほど、その苦難の淵が深ければ深いほど、彼女の言葉はより暗い絶望の泥沼にいる心に届くものになったのだ。 道なんかない、愛なんかこの世にはないと諦めなくていい。私が通った絶望と苦難を見てください、そこから私を救った愛、凍えた私を溶かしてくれた神の愛の温かさを知ってください。それは私だけの特別な物語じゃない。あなたにも用意されている道があり奇蹟がある。それが三浦綾子文学からほとばしるメッセージだ。圧倒的な愛の体験を証拠として希望を語ること、それはすべての信仰者にも勧められていることではないだろうか。

三浦綾子が40年通った旭川六条教会(筆者提供)
※『道ありき』は3部作で、この他にも『この土の器をも―道ありき第二部 結婚編―』『光あるうちに―道ありき第三部 信仰入門編―』(いずれも新潮文庫刊)があります。
