三浦綾子の人生と文学が語る信仰③
「道ありき」――極みまで愛すること
森下 辰衛(もりした・たつえ)
三浦綾子読書会講師
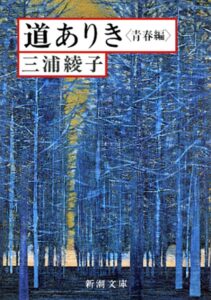
「愛されることは、ただ燃え尽きることだ。愛することは長い夜にともされた美しいランプの光だ。愛されることは消えること。そして愛することは、長い持続だ」(大山定一[おおやま・ていいち]訳)。
リルケ『マルテの手記』のこの二行は、前川正(まえかわ・ただし)特愛の言葉だった。彼は愛されることよりも、愛することを試みようとした。しかし、だからこそ、1949年6月の春光台(しゅんこうだい)で前川は綾子を立ち直らせることのできない自分をゆるせず、自らの足を石で打った。その時綾子は、彼の姿に今まで見たことのない光を見た。暗闇にうずくまっていた魂に再生が始まった。
「この丘の上で吾れとわが身を打ちつけた前川正の、わたしへの愛だけは、信じなければならないと思った。もし信ずることができなければ、それは、わたしという人間の、ほんとうの終わりのような気がしたのである」。(『道ありき』-青春編- 11章)
「丘の上で吾とわが身を打ちつけた」彼。そう書く綾子には十字架のイエスの姿が二重に映されているだろう。前川は、聖書を読むこと、祈ること、短歌を詠むことを勧めて、弟子のように綾子を導き育て、死までの5年余りに1600通の手紙を書いた。1950年1月12日の手紙に、前川はこう書いている。
「イエスこの世を去りて父に往(ゆ)くべき己(おの)が時の来(き)たれるを知り、世に在る己(おのれ)の者を愛して、極(きはみ)まで之(これ)を愛し給えり」(ヨハネ13・1、文語訳)の 「世に在る」以下です。「極まで之を愛し給えり」この言葉を、人間同士の愛にも使える人ははたしてあり得るでしょうか? 綾ちゃんとの友情、交わりということを反省して、常に私の心の中に、自分以外のものからの声として、この言葉が響いてくるのをきいています。
『生命に刻まれし愛のかたみ』
残された時間の少なさを悟った時、彼は「世に在る己の者を愛して、極まで之を愛」せよという声を聞き、従った。イエスが弟子を愛したように、堀田綾子を「極みまで」愛することが彼の最後の仕事になった。
ヨハネ13章のこの後にはイエスの洗足の記事が続く。足を洗われる弟子たちが戸惑いその意味を問うと、イエスは「今は分からないが、あとでわかる」と答える。弟子はあとでわかる。足で裏切って逃げたとき、足で日曜の朝墓まで走ったとき、足で福音を伝え歩いたとき、足に鎖され獣に食いちぎられた時、弟子たちはわかる。足を洗う主の心にあったのが、あらかじめのゆるしであり、祝福であり、涙と痛みの拭いだったのだと。その手に触れられた者は、後から後から終わらない祝福に満たされる。前川はこのイエスを生きて綾子にゆるしと祝福と励ましとの遺書を遺し、彼女は彼の足を忘れなかった。

三浦綾子『道ありき』文学碑。(旭川市春光台公園、筆者撮影)
※『道ありき』は3部作で、この他にも『この土の器をも―道ありき第二部 結婚編―』『光あるうちに―道ありき第三部 信仰入門編―』(いずれも新潮文庫刊)があります。
