ず ー と 〜沖縄の重荷を知る〜
富田 直美(とみた・なおみ)
市川大野教会[千葉]
聖書
同じように、わたしはあなたたちの老いる日まで
白髪になるまで、背負って行こう。
わたしはあなたたちを造った。
わたしが担い、背負い、救い出す
(イザヤ46・4)
賛美歌
「あきらめない」(第34回全国小羊会キャンプテーマソング)
おはなし
6月、沖縄では戦争で払った犠牲の重さを心に刻む「慰霊の日」があり、教会では「命(ぬち) どぅ宝」として、沖縄の重荷を分かち合うことを大切にしています。私たちは歴史の中で沖縄を「国外」と位置付けていた時代がありました。沖縄が負った痛みや苦しみを理解せずに、悲しい気持ちを考えることなく使ってしまった言葉です。
小羊会でつながっている友だちは日本全国にいますが、自分の住んでいる県だけが「平和で豊かであるように」と願っている人はいないと思いますし、もしも、どこかの県の友だちだけに不公平なことを押し付けている事態が起きて、友だちが苦しむなら、おかしいと気づいて「間違いだ、やめよう」と一緒に声を上げることができるでしょう。
6月になると沖縄県内の学校から『月桃(げっとう) 』という歌が聞こえてくるそうです。その歌は、沖縄が本土復帰して10年目に作られました。テレビ局は海勢頭豊(うみせど・ゆたか)さんに「本土(日本)に復帰して10年経ってもアメリカの基地はなくならず、事件や事故が繰り返されていることへの怒りを込めた歌を作ってほしい」と依頼しました。依頼を受けた海勢頭さんは、歌を作るために激戦地だった糸満(いとまん)市を取材のために訪ねたところ、目にしたのは、全滅した屋敷の跡地に鮮やかな月桃が花を咲かせている風景でした。その時に海勢頭さんが作らなければならないと思ったのは、怒りを込めた歌ではなく、沖縄戦の体験者の奥深くにある平和を願う心の歌だと思ったそうです。歌詞の中に直接戦争を表現する言葉はありませんが、「平和を語り継ぐ勇気を子どもたちに持ってほしい」との願いが込められていることが感じられます。
旧約聖書イザヤ書46章4節には、「わたしはあなたたちを造った。わたしが担い、背負い、救い出す」というみ言葉があります。私たちをお造りになった神さまが、「わたしが担い、背負い、救い出す」と言ってくださっていることは何と心強いことでしょう。平和を作るために声をあげることはとても勇気のいることです。でも、このみ言葉に励まされ、沖縄の方がたと諦めずに共に歩みましょう。
*『月桃』の歌の経緯については、「しんぶん赤旗」2023.8.23を参照しました。
*沖縄の歴史、「命どぅ宝」についての参考資料や祈りのリクエストなどは、女性連合のHPをご活用ください。
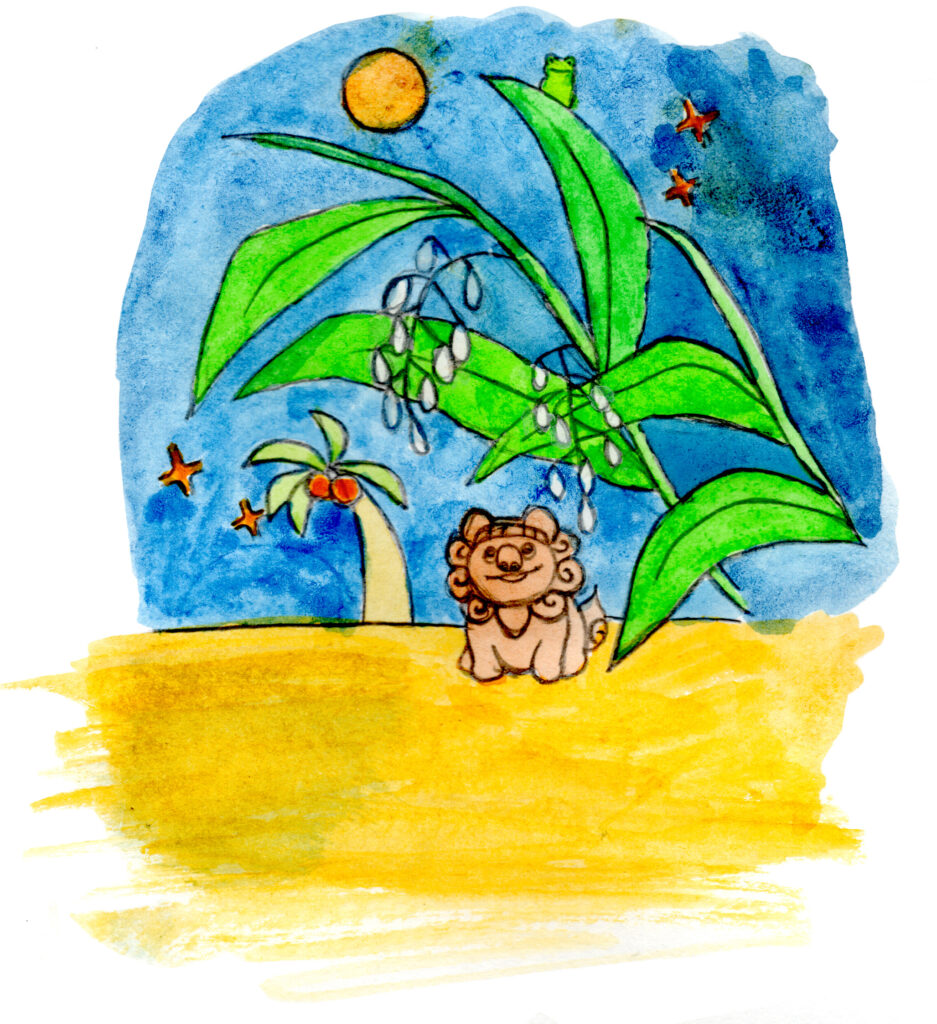
(イラスト:飯田 もも[筑波])
